📖美学No.78《楢山節考》
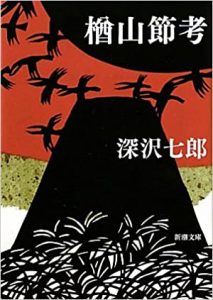
深沢七郎 著
山深い貧しい部落にある因習。それは口減らしのため、年寄りは70歳になると、我が子の背板に乗せられ真冬の楢山へ捨てられる。深沢七郎は、この「姥捨伝説」を農家の年寄りから聞いた。そして、肝臓癌を患い、自らの意思で死ぬために餓死を望んだ実母の死と重ね合わせて「楢山節考」を書いた。当時42歳の処女小説。1956年の第一回中央公論新人賞を受賞。名だたる評論家や作家達がこぞって衝撃を受け絶賛。選者であった三島由紀夫の批評が面白い。
《それは不快な傑作であつた。何かわれわれにとつて、美と秩序への根本的な欲求をあざ笑はれ、われわれが「人間性」と呼んでゐるところの一種の合意と約束を踏みにじられ、ふだんは外気にさらされぬ臓器の感覚が急に空気にさらされたやうな感じにされ、崇高と卑小とが故意にごちやまぜにされ、「悲劇」が軽蔑され、理性も情念も二つながら無意味にされ、読後この世にたよるべきものが何一つなくなつたやうな気持にさせられるものを秘めてゐる不快な傑作であつた。今にいたるも、深沢氏の作品に対する私の恐怖は、「楢山節考」のこの最初の読後感に源してゐる。》
「私とは?」「社会とは?」と、生きることや死ぬことをぐちゃぐちゃ考え、思い悩んでいた二十代に、ハマった。そんな面倒くさい思いは吹っ飛んだ。深沢七郎は「人間は屁のようなもの」とあっけらかんと語る。山田詠美、鷺沢萠など、私の好きな女性作家たちも、好きな作家として彼の名前を挙げている。うなずける。決して美しい文章ではない。が、美辞麗句を書き連ねた文章よりも、根底にある自然なエネルギーとでもいうようなものが、ページをめくらせる。《明るいニヒリズム……肯定そのものが無であって、無そのものから肯定が出てくるような》と、小説家にして僧侶の武田泰淳は言っている。
深沢七郎は、エルヴィス・プレスリーの大ファン。職を転々としながらギター奏者として日劇ミュージックホールに出演。土俗的な独自の作品を発表し続け、51歳で「ラブミー農場」を開き、6年後、東向島に今川焼屋「夢屋」を開く。その包装紙は横尾忠則が描いた。1987年73歳、床屋の椅子に座り、昼寝をしたまま亡くなる。彼の人生観そのもののような最期。

二十代前半、出版社の試験を受けた。筆記試験に「好きな作家」とあったので、「深沢七郎」と書いた。面接で「深沢の世界は赤だと思う?白だと思う?」と聞かれた。試験の合否も覚えていないのに、その質問だけは今でもはっきり覚えている。私の答えは「白」だった。
